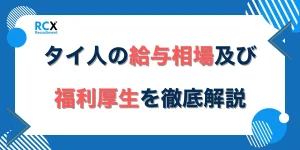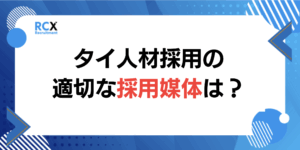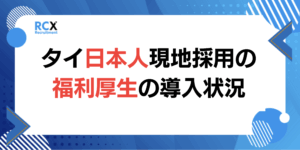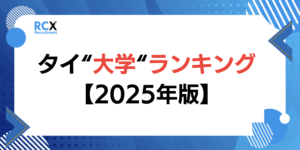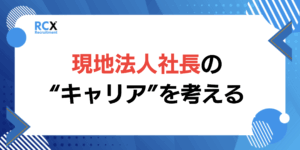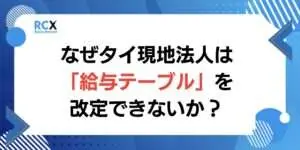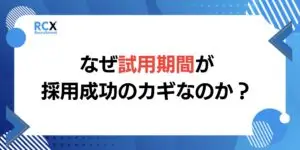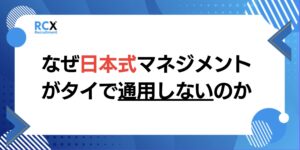海外法人を安定経営に必要な「共通ルール」の設定
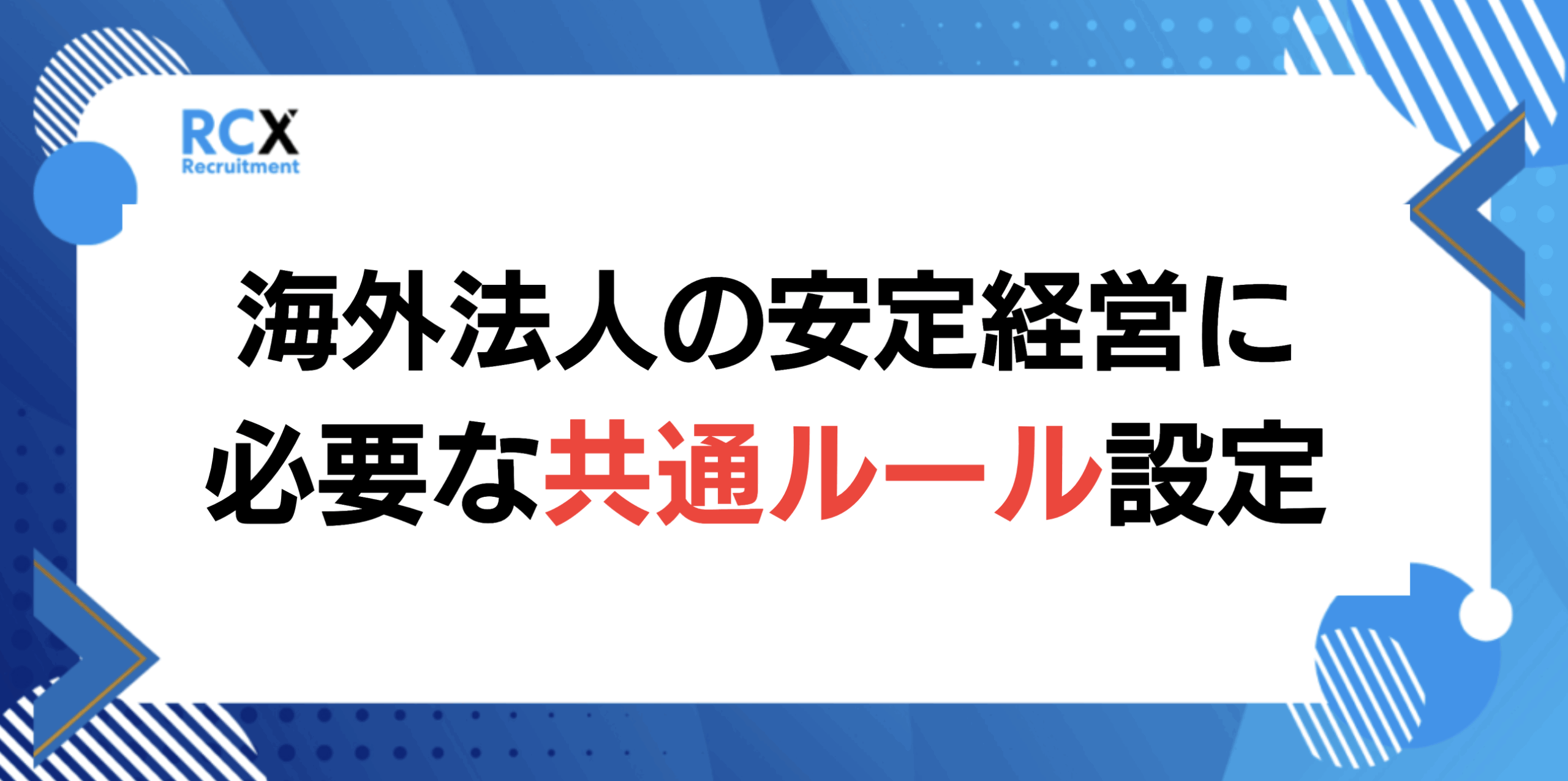
なぜ海外拠点のマネジメントは難しいのか
タイ法人を始め、海外拠点を運営する日系企業が必ず直面するのが、現地スタッフとの「商習慣の違い」によるマネジメントの難しさです。
例えば、「始業時間を過ぎてから朝食を取り始める」、「数分の遅刻を繰り返す」、「業務中に私用SNSや電話をする」──日本では違和感のある行動が、現地では日常的に見られます。
そして、こうした行動に対し、日本人管理者が注意しても改善されないどころか、怒られる側が「なぜ自分が叱られているのか」を理解できず、関係性だけが悪化してしまうこともあります。これは、そもそも前提となる価値観が異なるに他なりません。
このような状態を放置しておくと、チーム全体の士気低下、優秀人材の離職、生産性の低下、といった深刻な問題に発展します。
では、どうすればいいのでしょうか? その答えが「共通ルールの設定」です。
属人マネジメントの限界と、ルールによる仕組み化
日本では、同じ価値観の日本人が集まり、”阿吽の呼吸”や”空気を読む”が通用するため、共通のルールがなくとも組織が機能する傾向があります。
一方、これは価値観の異なる海外では通用しません。文化や価値観の異なる人材をマネジメントするには、「誰にとっても分かりやすく、解釈にブレがないルール」が必要不可欠となります。
確かに多くの会社でも、口頭ルールを含め、一定のルールがあると思います。しかしながら、正しいルールの設定とその周知徹底がなされていなければ、必ず形骸化します。
ルール設計のポイント:現地拠点に必要なルールとは?
では、どのようなルールが必要か。例えば、以下のようなルールがあります。
- 始業時間(例:8時)までに朝食・着替え・化粧を完了しておくこと
- 1分の遅刻も遅刻としてカウントする
- 遅刻・早退・欠勤時は事前に上長へ連絡を入れる
- 私用SNSや個人電話は禁止
- 業務外出や直行直帰には必ず事前許可を得る
これらは一見当たり前のことですが、日本人とは仕事の善悪の基準が異なる海外においては、ルールとして明文化されていない場合、現地スタッフにとっては”大きな問題ない”と認識されてしまうことが多いです。
ゆえに明確な共通ルールが必要となるのです。重要なのは、価値観を押し付けるのではなく、「全員が同じ基準で動けるようにすること」です。
成功するための3ステップ:「設定」「浸透」「運用」
ただし、どれだけ良いルールを作っても、それが現場で機能しなければ意味がありません。ルールを“生きたもの”として機能させるには、以下の3ステップが不可欠です。
1. 設定(ルール設計)
まず大切なのは、「シンプル」で「人によって解釈がズレない」ルールを設計することです。たとえば「赤信号では止まる」というルールは、誰にとっても明確で、解釈の余地がありません。
これと同じように、職場においても複雑・曖昧なルールは極力排除し、誰が見ても同じ意味に捉えられる内容にすることが重要です。ルールは組織運営の“入口”となるため、ここがズレると、すべてがズレ続けてしまいます。
2. 浸透(ルールを定着させる)
どれだけ優れたルールを定めても、現場に浸透していなければ意味がありません。「赤信号は止まる」が社会に浸透しているのは、家庭や教習所などで繰り返し教育されるからです。
同様に、職場でも「就業規則への明記」「試用期間の評価基準として明示」「評価制度との連動」「ルール理解度テストの実施」など、仕組みとして周知徹底することが欠かせません。
3. 運用(ルールを守らせる仕組み)
最後に必要なのが、ルールを「守らせる仕組み」です。たとえば「赤信号では止まる」という行動が守られる背景には、取り締まりや罰金といった抑止力が存在します。職場においても、ルールを形骸化させないためには、「罰則」あるいは「報酬」といった仕掛けが必要です。
たとえば遅刻に対しては、以下のような段階的な罰則を設ける方法があります。
罰則:月4回以上の遅刻で警告対象とする
・1回目:口頭警告
・2回目:書面警告
・3回目:出勤停止3日間
・4回目:解雇(※現地の労働法に準拠)
ここで重要なのは、「どのような違反に対して、どのような罰則が科されるのか」を、誰が見ても同じ判断になるレベルまで明確にすることです。判断基準を“人”に委ねるのではなく、“ルール”に委ねることで、解釈のズレを防ぎ、現場で発生しがちな無駄なストレスややり取りを減らすことができます。
ルールの運用主体はHRへ
判断が標準化されれば、その運用は人事部門(HR)に委ねることができます。ルールに基づいて、HRが事務的かつ中立的に対応することで、属人的な判断を避けることができます。
さらに、運用がHRで形骸化しないように、「ルールの運用状況」をHRの評価項目に組み込むことが重要です。これにより、HRも当事者意識を持ち、ルール運用が組織の仕組みとして定着していきます。
この体制が整うことで、属人性を排除し、「仕組みで動く組織」へと転換することが可能になります。日本人管理者は、個別に指摘を繰り返すストレスから解放され、本来注力すべき自身のミッションに集中できるようになります。
マネジメントとは、特定の個人に頼るものではなく、”明確な仕組み”と”役割分担”によって成立させるべきものです。これこそが、海外におけるマネジメントの理想的な在り方と言えるでしょう。
具体的に何をルール化すべきか?
実際にどのルールを設定すべきかは、国情や業種・職種、そして自社の状況によって大きく異なります。
以下に、東南アジアの新興国でのマネジメントにおいて導入を検討すべき「36のルール項目」をチェックリストとして整理しました。
自社で課題を感じている点があれば、ぜひ参考にしてください。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 始業の定義 | どのような状態で始業開始(給与発生)と認めるのか (着替え・化粧・朝食などは始業時間までに済ますなどルール設定) |
| 残業の 承認プロセス | 会社に居残るだけで自動残業発生を避けるため、残業は事前申請制度と設定する。 |
| 副業の規定 | 海外では副業は一般的であるが、業務時間の副業は禁止するという条件を設定すべき。 |
| 業務中の タバコの取り扱い | 渋滞が酷いエレベータの場合、タバコ休憩に20分かかる。 他のスタッフとの公平性を保つために業務中は禁止など設定する。もしくは喫煙者採用しないなど。 |
| 業務中の SNSの取り扱い | 仕事でSNSを使用しない職種の場合、私用のSNSは原則禁止とすべき |
| 業務中の 食事の取り扱い | 朝食は始業時間前、ランチはランチタイムに食べると設定する。設定しないと始業後に朝食を食べ始めるのことが起きる。また、商談などで食事時間がズレる場合は上長から許可を取る。 |
| 業務中の外出 | 原則外出は禁止とする。必要な場合、理由を上長に伝え、承認を取る。 |
| 直行直帰 | 直行・直帰は何時アポだったらOKか。13時アポで直帰するなどを避けるため。 |
| 早退・欠勤の 報告ルール | 早退・欠勤時は、何時までに誰から許可を取るかの設定。 事後報告を避ける。設定しておかないと事後報告だらけで制御不能に。 |
| 遅刻の事前連絡 | 遅刻時は出社時間までに上長に連絡をいれる。事後報告を避ける。 |
| 有給休暇の 計算方法 | 期の途中入社の有給休暇日数の取り扱い。月割で計算するのが無難。 |
| 有給休暇の付与 のタイミング | 正社員になった後に有給の権利が発生するのか、どのタイミングで新しい年の有給が付与されるのか。 |
| 有給休暇の取り方 | 3営業日前に申請が必要などの期日設定が必要。 |
| 未使用の有給の 処理方法 | 使わなかったものを買い取る、翌年に持ち越しなどを決める。※各国の法律要チェック |
| 病欠の取り方 | 多くの国では病欠が有給となる。3日以上連続で病欠を取る場合は診断書の提出の義務化する。 年間10日以上使用する場合は人事評価でマイナス評価するなど抑止が必要。 |
| 勤務時間の単位 | 給与計算の単位を10分単位、1時間単位などどう設定するか、 1時間単位の場合、1分遅刻したら、1時間分給与が減給される。※各国の法律要チェック |
| 勤務地 | 個人情報を取り扱う業種で、リモートワークを取り入れている場合は、 カフェなどオープンな場所での仕事は禁止。自宅など事前登録している場所に限定する。 |
| リモートワーク の環境条件 | 安定したインターネット環境・パブリックな場所の禁止・オンラインMTGが可能な 静かなスペースの確保を義務付ける。設定しないと旅先から勤務する人間が出てくる。 |
| リモートワーク の許可条件 | リモートワークを実施するためにはパフォーマンスが一定以上であることを設定する。 |
| リモートワーク の取り消し条件 | リモート給与泥棒を避けるために 3ヶ月連続目標未達はリモートワーク取り消しなど取り消し条件を設定する。 |
| 服装 | ルールを設定しないとサンダルや短パンで出社する社員が出てくる。 |
| 業者からの キックバック禁止 | 人によっては悪気なく業者や仕入先からキックバックを受け取るので、明確に禁止とすべき。禁止にしないと質は悪いがキックバックが高い業者が選定されるリスクあり(これは良く発生するので要注意) |
| 社内情報の 取り扱い | 機密情報に関する基準が日本人と異なる。 顧客データ・財務データなどどの情報が外部共有不可の機密情報に当たるかの設定する。 |
| 試用期間の 通過条件 | 試用期間通過のためのパフォーマンス条件・査定時期を設定する。 |
| 正社員後の 給与設定 | 正社員後に給与が上がるか、そうでないかを明確にする。 |
| 退職の手続き | 退職時は、何日前に報告するのか、引き継ぎのルールなどを決めないと 引き継ぎ無しで退職する人材が続出する。 |
| 退職時の 備品返却の条件 | パソコン・携帯・カギなど会社の備品を返却することを明確にする。 返却ない場合は、最終の給与の差し押さえも記載する。※各国の法律要チェック |
| ルール違反 の罰則 | 例えば、最初の違反:口頭警告→2回目:書面警告→3回目:出勤停止→4回目:解雇など、 同じ違反を繰り返した場合、罰則を厳しくしていく。※各国の法律要チェック |
| 解雇に 該当する行為 | 一発で解雇となる重大な違反の設定(横領・薬物使用・経歴詐称・社内不倫など)※各国の法律要チェック |
| 経費の 承認プロセス | 後出しジャンケンのような思わぬ経費申請を避けるために、一定以上の金額は事前承認が必要とする。 |
| 経費精算 のタイミング | 会社が都度経費の建て替えなどをしていると工数がかかる。 一定金額以下は個人建て替えとし、給与で払うなどを規定する。 |
| 備品の破損・ 紛失について | 携帯・PCなど会社の備品を紛失・破損した際は、弁償するルール設定する。 |
| 売上目標の 設定方法 | 会社は売上目標を上げたいが社員は低くしたい。 無用な交渉を防ぐため、基本給与とリンクさせるなど設定が必要。 |
| 給与 | 給与の締め日と支払日・支払い方法。日本でたまにある月末締めの月末払いは遅すぎる。 長くても締め日から10日で払う必要がある。※各国の法律要チェック |
| 賞与の支給 | 賞与を払う時期、賞与の計算方法、賞与を払えない条件(業績不振時など)の設定する。 |
| コミッション | コミッションの計算方法、支払条件(顧客からの入金したら)などを設定する。 |
| 通勤手当 | 海外は日本のように公共交通機関が発展していないため、計算が難しい。 首都圏はいくら、首都圏外はいくらなどシンプルな設計にする。または一律払わない。 |
| 評価制度 (給与査定) | 査定時期・査定方法の明確化する。基本的に年1回の査定が多い。 |
上記は参考になります。法的に問題ないかは現地の弁護士などに確認する必要があります。
おわりに
私は11年前、フィリピン法人の立ち上げ時に、自身の未熟さから組織崩壊を招き、従業員から複数の訴訟を受けるという苦い経験をしました。
この反省から、「基準のない属人的なマネジメント」から、「ルールに基づくマネジメント」へと方針を転換しました。
その結果、生産性は大きく向上し、ローカル人材の離職率も大幅に減少しました。この手法はタイやベトナムでも有効に機能しており、再現性の高いマネジメント手法であると実感しています。
マネジメントとは、個人の能力に頼るのではなく、組織が再現性を持って回る仕組みをつくることです。特に文化や価値観が異なる海外拠点では、この「仕組み化」が成果を大きく左右します。