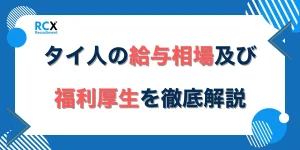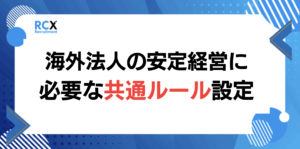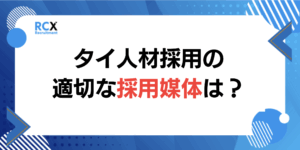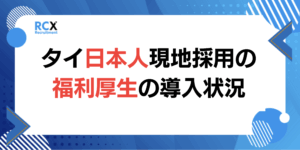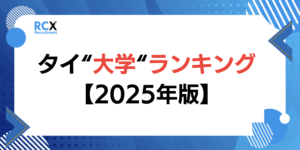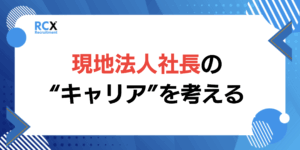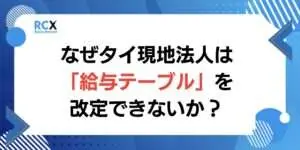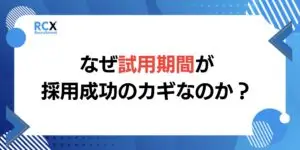なぜ日本式マネジメントがタイで通用しないのか
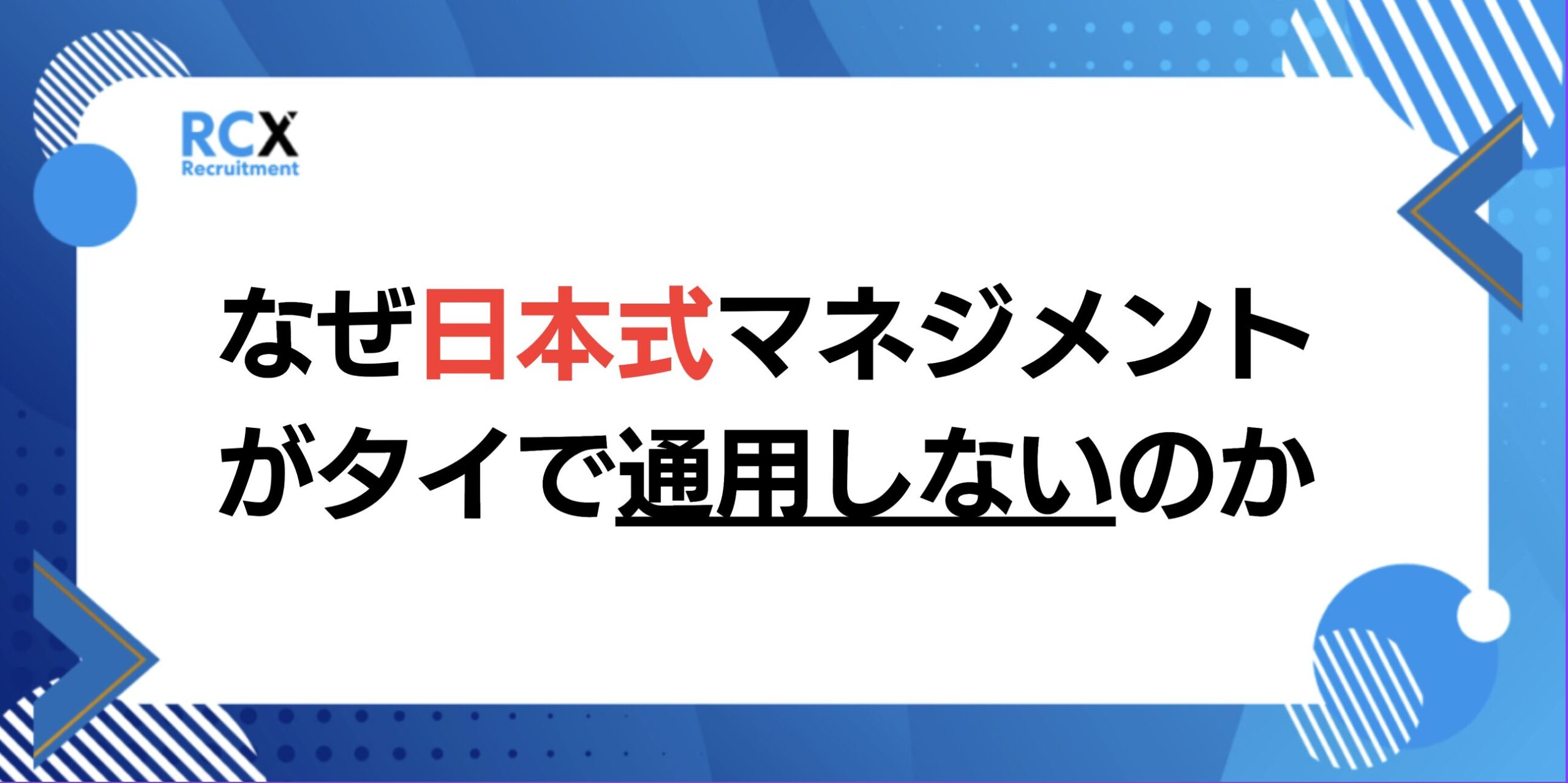
近年、海外法人の責任者として多くの日本人が海外に赴任しています。しかし実際には、「思っていたのと違う」と悩み、現地でマネジメントに苦戦するケースが後を絶ちません。
「語学力」や「経験不足」が原因とされがちですが、本質的な課題はそこではありません。
最大の原因は、「日本と海外では、マネジメントに求められる型がまったく違う」ことにあります。
本記事では、日本人がなぜ海外でマネジメントに失敗するのか、そして何を重視すべきかを、組織運営の視点から解説します。
海外赴任でよくある“落とし穴”
意気揚々と海外に赴任し、その後間もなく、「こんなはずじゃなかった」と肩を落とす日本人責任者を何度も見てきました。
その原因は、語学力でも人間力でもありません。
それは、「海外でのマネジメントは日本でやってきたいマネジメントの延長にない」からです。
マネジメントには2つの型がある

マネジメント手法は、大きく分けて次の2種類に分類されます:
1. 個人マネジメント(個別対応型)
リーダーが、メンバー一人ひとりと密に関わり、信頼関係を築きながら成長を促すスタイルです。
- 1on1ミーティング
- 丁寧な指導やサポート
- 飲みニケーション
などが代表例です。一般的な日本人に経験があるのは、このスタイルのマネジメントが中心となります。いわゆるチームリーダー的なマネジメントになります。
2. 組織マネジメント(仕組み構築型)
個人に頼らず、組織として回る仕組みを構築するスタイルです。
- 共通ルール
- KPI
- 評価制度
- 就業規則
組織そのものを対象としたマネジメントです。個別対応ではなく、共通のルールを整えることによって、組織全体の生産性を底上げします。
ここでは、マネージャーの主観による判断ではなく、明文化された「基準」が中心になります。
海外で求められるのは「組織マネジメント」
海外の現場では、前者の「個人マネジメント」はほとんど機能しません(少人数の例外を除く)。理由はシンプルです:
- 言語の壁により、言いたいことの70%しか伝わらない
- 商習慣の違いにより、相手も70%しか理解できない
結果として、伝達率は約49%(70% × 70%)。
このギャップを埋めようとすれば、日本の2倍以上の労力がかかります。
様々なミッションを抱える日本人駐在員にとって、それは非現実的です。
トップは「チームリーダー」ではなく「経営者」になるべき
求められるのは、“個に委ねる”のではなく、“基準で判断する”組織の構築です。
- 共通ルール・評価制度・就業規則・KPIを整備し
- 採用・育成・評価・昇格・解雇を、そのルールに基づいて運用する
マネジメントの現場で逐一トップが判断するのではなく、ルールが判断してくれる状態を作る。これこそが、海外法人における日本人トップの「経営者としてのマネジメント」です。決して、日本人マネジメント層がチームリーダーのように個人に深く入り込みすぎてはいけません。
組織マネジメント未経験者が陥る落とし穴
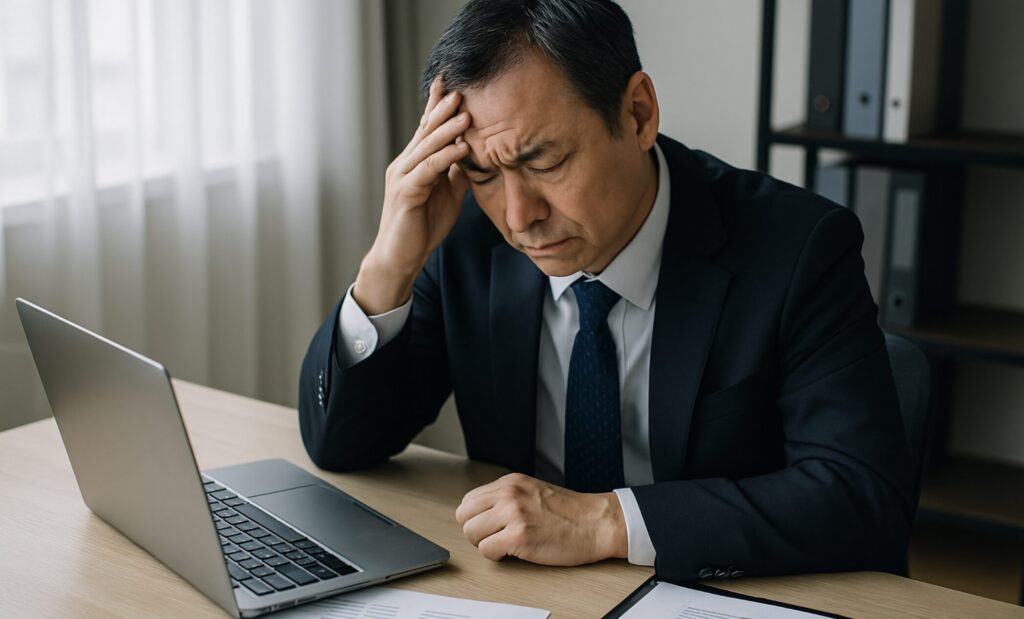
多くの日本人駐在員は、「チームマネジメント」の経験はあっても、「組織マネジメント」の経験がありません。
その結果、
- 過干渉なマイクロマネジメントで信頼を失う
- 放任型マネジメントで現場が混乱する
という両極端の失敗に陥ることが多く見られます。
海外でのマネジメントは、「個人の力」ではなく「仕組みの力」で動かすものです。属人的な方法ではなく、組織として再現性のある運用を実現する。
それが、グローバルで活躍する日本人リーダーに求められる、真のマネジメントスキルなのです。