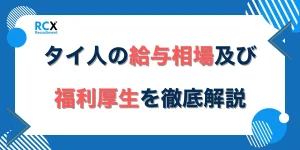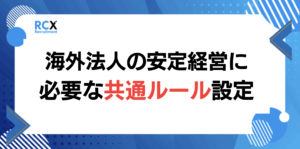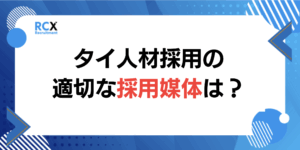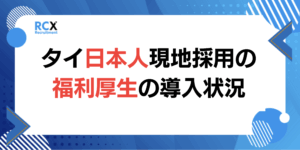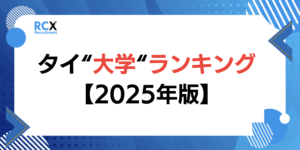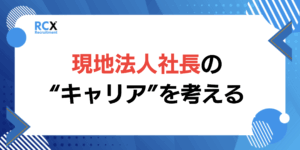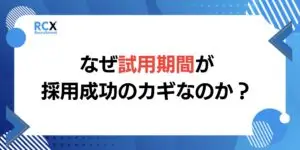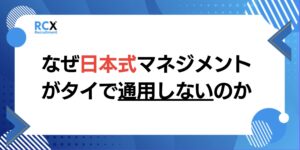なぜタイ現地法人の給与テーブルを市場相場に合わせて改定できないのか。

~タイの採用現場から見える、日系企業共通の課題~
タイでの人材採用において、「給与条件が合わずに内定辞退される」「良い候補者が採れない」と感じることはないでしょうか。
この問題は、タイに限らず、東南アジアや他の海外拠点でも共通して見られる傾向です。
本記事では、タイの現地法人で実際に起きている課題を切り口に、「なぜ給与テーブルが変えにくいのか」を整理しました。
駐在社長の皆様のご判断の一助となれば幸いです。
1. 「本社基準」がタイ現地法人の意思決定を縛っている

タイの物価や人件費が上昇を続けるなかでも、給与テーブルや昇給率が、日本国内の低成長に準じて「本社基準の控えめ」に設定されている企業は少なくありません。
これは一見、健全なコスト管理に見えますが、実際には現地の人材市場との間にズレが生じ、採用難に直結しています。
同様の現象は、これはタイに限らず、他のASEAN諸国でも同様であり、結果的に“現地市場との乖離”が採用難を引き起こしている構図です。
2. 駐在社長が抱える任期と制度改定のジレンマ
現場で人材獲得に苦労している駐在社長の方々も、「給与制度の見直しが必要だ」と日々感じておられるはずです。
しかし、3年ほどの任期内で「給与テーブルの改定」「本社との交渉」「人件費予算の再設計」まで踏み込むのは、時間的にも組織的にも大きな負荷を伴います。
実際、多くの現場では「いまは動かさない」「次の任期者に委ねよう」という判断になりがちです。
3. 「先送り」が招く、採用力の低下

制度改定が先送りされることで、昇給テーブルや給与基準は何年も変わらないままになりがちです。
結果として、優秀な人材にはオファーが届かず、辞退・離脱が繰り返され、現場では「採れない/辞める/定着しない」が慢性化していきます。
この「静かな機会損失」は、企業の競争力をじわじわと蝕んでいきます。
4. 柔軟な企業との採用力格差が拡大中
一方で、給与テーブルが柔軟な日系スタートアップやオーナー企業では、現地相場に即した柔軟なオファーができており、優秀な人材を着実に確保しています。
特に、他の選択肢がある優秀な候補者やマネージャー層は、オファー額が採用成功に直結するため、「給与テーブルが動かせない」という事情は、採用力に直接影響を与える要因になっています。
給与テーブルの柔軟性が、企業間の競争力を分けているのが実態です。
5. 現地人材は「企業の国籍」ではなく「成長と収入」を重視している
「日系企業だから応募が来ない」という声を耳にすることがありますが、それは正確ではありません。
現地の求職者が重視しているのは、「どれだけ稼げるか」「どれだけ成長できるか」という極めて実質的なポイントです。それゆえ、企業のどこの国籍は気にしていないのが現状です。
つまり、日系企業であっても、
- 市場水準に合ったオファー
- 魅力的な業務内容・キャリアパスが提示できれば、十分に優秀な人材を確保できます。
6. 採用力は事業競争力そのもの
私は、これまでフィリピン・タイ・ベトナムで2,500社以上の日系企業に対して、累計1万人を超える採用支援をしてきました。
その中で確信しているのは、「採用力=競争力」であるということです。
どれだけ優れた戦略があっても、それを実行できる人材がいなければ前に進むことはありません。
おわりに

駐在社長の皆様にとって、制度に踏み込むことは大きな挑戦であると理解しております。
だからこそ、「ギャップの見える化」や「小さな提案の積み上げ」が、将来の採用競争力を守るための現実的なアプローチになると考えています。
タイに限らず、他国でも同様の課題は顕在化しつつあります。
今後の採用戦略を検討する上での一つの材料として、ぜひご一読いただけますと幸いです。