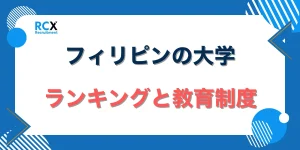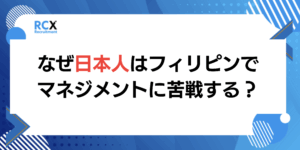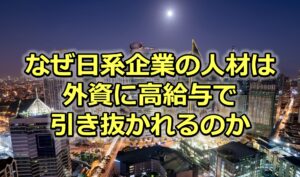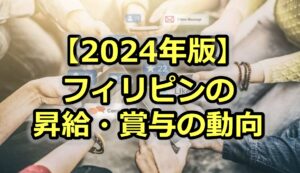なぜフィリピン現地法人の給与テーブルの改定が難しいのか?

~現場に立つ駐在社長の“本音と現実”から考える~
フィリピンでの採用活動において、「内定辞退される」「優秀な人が採れない」と感じた経験はありませんか?
本記事では、日系企業がフィリピンで直面する「なぜ給与テーブルが変えにくいのか」を整理してみました。
現場の皆様の葛藤や限界に共感しつつ、少しでも前進するヒントとなれば幸いです。
1|「日本本社の基準」が、現地の実情を縛っている
フィリピンでは物価も人件費も年々上昇していますが、日本本社の低成長を背景に、
多くの企業では本社主導の「抑制的な給与テーブル」が続いています。
もちろん、本社としては全拠点のコストコントロールの観点で合理的な判断です。
しかし現場では、その給与水準が現地市場の実態とかけ離れたものとなり、採用の足かせになっています。
本社基準との“板挟み”にある駐在員にとっては、分かっていても動かせない苦しさがあります。
同様の現象は、フィリピンのみならず、他の東南アジア諸国でも起きており、採用難を引き起こしている背景となっております。
2|任期と制度改定のジレンマに悩む現地責任者たち
現場で人材獲得に苦労している駐在社長の方々も優秀な人材採用には「給与制度の見直しが必要だ」と日々感じておられるはずです。
ただし、「このままでは採れない」と思っても、3年程度の任期では、「給与テーブルの改定」「予算の再編成」、「制度設計の見直し」、「稟議ルートの整理」を本社と交渉しながら進めるには時間的に組織的にも大きな負担がかかります。
そして多くの駐在社長には、数年で交代する立場で、将来に責任を持つ改革に踏み込むのは、プレッシャーも大きいという結論になってしまいます。
それゆえ、「今やるのは得策ではない」「次に引き継ごう」と判断せざるを得ないのは、現実的な選択なのです。
3|動かない制度が、採用の“静かな機会損失”を生む
制度が据え置かれたままになると、昇給の仕組みや給与基準が古くなり、
そのままでは優秀な人材の要望に届かないオファーしか出せなくなります。
「辞退された」「すぐ辞めた」「定着しない」といった現象が続き、現場は慢性的な人手不足に。
見えにくいですが、このような“静かな機会損失”こそ、企業にとって最も致命的な損害となります。
4|柔軟な給与設計ができる企業に、採用競争で後れを取る
一方で、オーナー企業やスタートアップのように、現地でスピーディに動ける企業は
市場水準に即した給与オファーをタイムリーに出せています。
特にマネジメントクラスやスキル人材では、給与の柔軟性が採用成否を分ける要因になります。
「硬直的な給与テーブル」は、採用力に大きく影響します。
5|求職者が見ているのは「成長性」と「待遇」である
「日系だから応募が少ない」と聞くこともありますが、
実際のフィリピン人求職者は、企業の国籍よりも、
- 自分が成長できる環境か
- 適正な報酬が得られるか
という合理的で現実的なポイントで判断しています。
つまり、たとえ日系企業であっても、魅力的な仕事と待遇を提示できれば採用は可能です。
6|採用力=競争力である
私は、これまでフィリピン・タイ・ベトナムで累計2,500社超の採用支援を行ってきました。
その経験から断言できるのは、採用力こそが企業の競争力そのものであるということです。
戦略がどれほど秀逸でも、それを実行する人材がいなければ、企業は動きません。
採用できるかどうかが、事業の成否を分けるのです。
おわりに|すべてを変えなくても、第一歩は踏み出せる
制度に踏み込むことは、駐在社長にとっては大きなリスクでもあり、覚悟の要る決断です。
その現実を十分に理解した上で、今できる小さなアクションとして、
- 現行制度と市場水準の“ギャップの見える化”
- 一部職種・ポジションだけでも試験的に柔軟対応
といった対応が、将来の採用力を守る現実的な道筋となります。
フィリピンに限らず、他国でも同様の課題は顕在化しつつあります。
この記事が、現場で戦う皆様の判断を後押しする材料になれば幸いです。